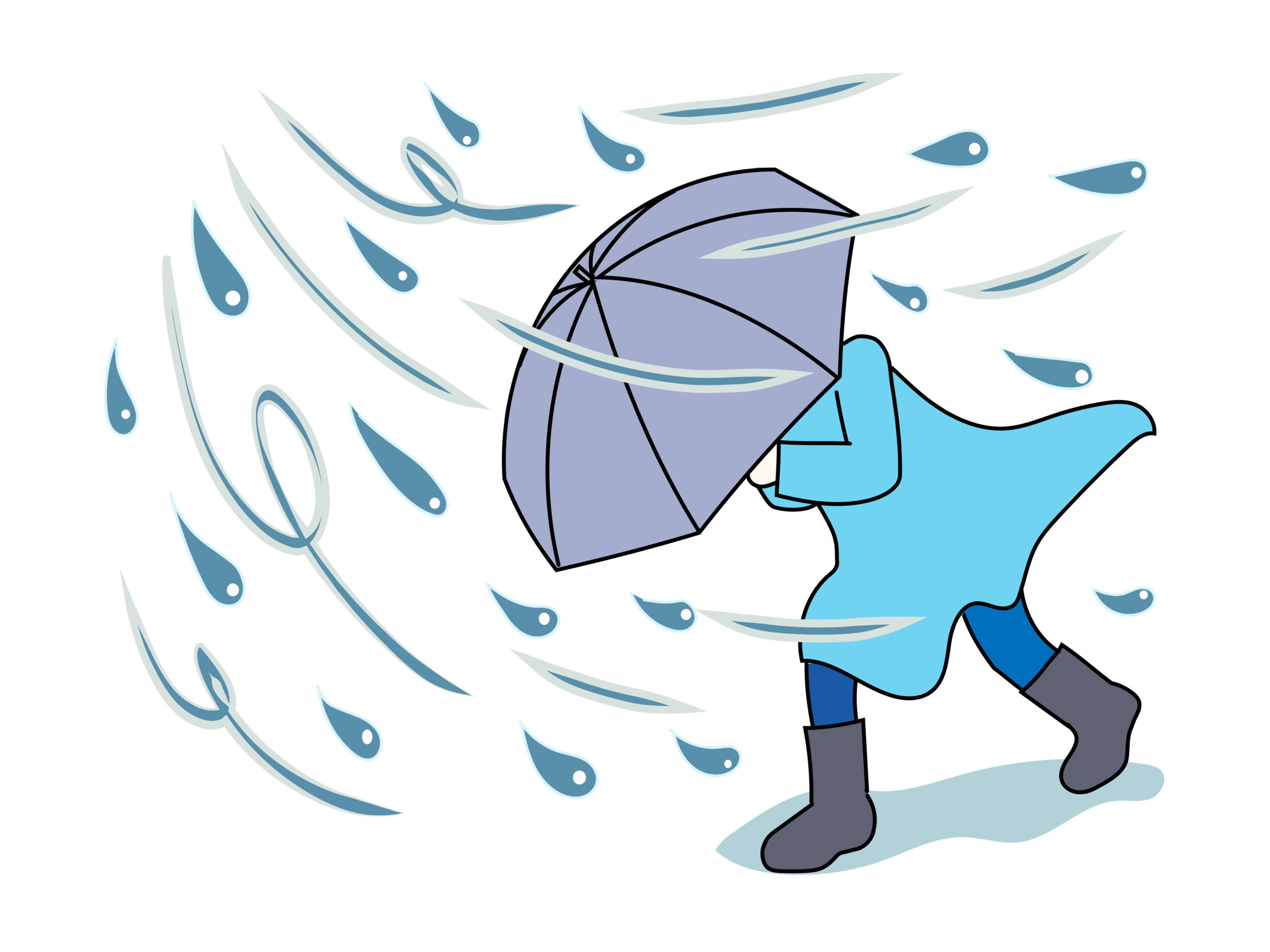最近、気候変動のせいで、普段とは違う激しい天気に驚かされることが多くなりましたね。
特に梅雨や台風の季節には、大雨警報の発令がよくあります。
このような時、お子さんを持つ保護者の方々は、学校がどのように対応するのかとても心配されるでしょう。
「どうしてこんなに雨が降っているのに学校が休みにならないの?」
「なぜ地域によって学校の対応が異なるの?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。
この記事では、
- 大雨警報が出たときに学校がどのように対応するのか
- なぜ地域によって対応が異なるのか
をやさしく解説していきます。
大雨警報が出ても学校が休みにならない訳と地域ごとの基準

大雨警報が出た日でも、多くの地域では学校の授業が通常通り行われることが多いですね。
これには、大雨警報だけでは公共交通機関が停止するほどの影響がないためという理由があります。
ただし、地域によっては異なる対応がされることも。
それぞれの地域が独自の判断をしているためです。例えば、
- 大阪府では各市町村が自分たちの基準を持っており、土砂災害のリスクが高い地域では、大雨警報だけで学校を休むこともあります。
- 箕面市の場合、土砂災害警戒区域の学校は大雨警報と土砂災害警戒情報が同時に出されると、すぐに休校になります。
- 神戸市では、1時間に50ミリ以上の雨が降ったり、河川の水位が警戒水位を超えたりすると、校長が臨時で休校を決めることができます。
- 和歌山県の沿岸部では、各学校が独自の警戒基準を設定しています。
学校では、休校を決める際に次のような点を考慮しています:
- 通学路の安全性(冠水や土砂災害の危険性)
- 公共交通の運行状況
- 地域の地形や過去の災害の歴史
- 周辺河川の水位
- これからの天気予報
例えば2023年7月、京都市の山間部の小学校では、橋の水位が急に上がり、事前に休校が決定されました。
どんな気象警報で学校が休校になるかと具体的な例

大雨警報以外にも、以下のような警報で学校が休校になることがあります。
- 暴風警報:強風で通学中の生徒に危険が及ぶ可能性があるため、看板が飛んだり物が散乱することが理由です。
- 大雪警報・暴風雪警報:積雪や視界の悪さが生徒の安全に直接影響するため。
- 特別警報:非常に稀で極端な気象状況が予想される場合、ほとんどの学校で休校となります。
2024年に関東地方で突風による事故が発生した後は、暴風警報時の休校基準がより厳しくされました。
北陸地方では、大雪警報が発令された場合に「24時間で50cm以上の積雪」が休校の目安とされています。
学校でのICT活用:休校時も続く授業の工夫

気象警報が出ても、子どもたちの学びが止まらないよう、最近では多くの学校でICTを使った新しい取り組みが広がっています。
特に注目されているのは、オンラインで授業を行う方法です。
たとえば、東京のある中学校では、次のような対応をしています:
- 朝8時までに警報が出た場合、その日の授業は全てオンラインで行います。
- 授業中に警報が出た場合、午後からはオンライン授業に切り替えます。
- 下校時間に警報が予想される場合は、生徒を早めに帰宅させ、家でオンライン補習をします。
また、神奈川県のある小学校では、ハイブリッド授業を導入し、警報が出たときには対面とオンラインの授業を選べるようにしています。
以下のようなICTの取り組みも始まっています:
- 校内に気象観測システムを設置
- AIを使った気象予測と通学路の安全評価
- クラウドでデジタル教材を共有
- オンラインで朝礼やホームルームを実施
- 双方向通信が可能な学習支援アプリの利用
保護者が知っておくべき新しい学校との連絡方法と対応
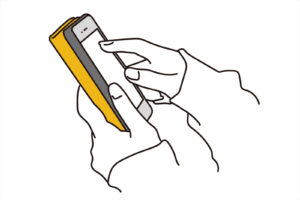
気象警報が発令された際の学校の最新対応をお知らせします。
多くの学校では、メールやLINEを使った緊急連絡体制を整えています。
保護者は以下のように準備しておくと安心です:
- 学校の緊急連絡網に事前に登録しておく
- 気象情報を提供するアプリをインストールする
- 複数の避難経路を確認しておく
- 通学路の危険箇所を確認する
- 緊急時の連絡先リストを作成する
- 携帯電話やモバイルバッテリーを予備で用意する
- オンライン授業用の機器設定を確認する
公式の警報が出ていなくても、自宅周辺の状況やお子さまの体調に応じて、自宅での学習を選択することが可能です。
その場合は、学校に連絡を忘れずにしましょう。
保護者と学校の連携を強化するために、以下のような取り組みが行われています:
- 保護者向けの気象情報講習会を開催
- 通学路の安全を確認する合同点検
- 緊急時対応のシミュレーションを実施
- オンラインでの保護者会を開催
- 気象警報に対する対応マニュアルを配布
まとめ
地域によっては大雨警報時の休校判断が異なりますが、どの学校も最優先で考えるのは児童・生徒の安全です。
学校の方針をしっかり確認し、わからないことがあれば積極的に学校に相談しましょう。
気象警報への対応は、安全を第一に考え、落ち着いて適切に対応することが大切です。
保護者と学校が連携して、子供たちの安全を守りながら、教育機会も確保していく努力が求められています。